スイスという「黄金の鳥かご」を抜け出したスイス人たち
在外スイス人7人のポートレートスイスという「黄金の鳥かご」を抜け出したスイス人たち
ニクラウス・ミュラー
将来のビジネスプラン成長し続ける中国に、将来の光を見出す文・Susan Misicka 写真・Daniele Mattioli
ニクラウス・ミュラー 上海で勉強中
ニクラウス・ミュラー 上海で勉強中


中国は自分の居場所だと言う。過去5年で、今回の滞在は3回目になる。ミュラーさんのように世界を見て回り、そこから得た経験を仕事などに生かす姿勢は、同年代のスイス人なら珍しいことではない。
だがミュラーさんが他と少し違うのは「流れに逆らって泳いでいる」から。ミュラーさんはスイスインフォの取材に「友人の多くは西側諸国に行きたがったが、私は東側だった。中国はとても魅力的な国。ここに来て2年以上経ったが、中国という国、世界経済の真っただ中にあるこの国をもっと知りたいと思った」と話す。
身ぎれいな服装で、インタビューには事前に作ったメモを持参していた。熟慮型できちんと準備をする人柄なのだろう。もともとはベルン出身。2011年、国際法律事務所CMSのインターン生として初めて中国の地を踏んだ。翌年には司法試験のためチューリヒに戻らなければならなかったが、中国のことは常に頭にあった。
ミュラーさんは「スイスにいる間にはもう、何とかして中国へ戻らなければと考えていた」と振り返る。上海に戻り、インターン先のCMSで雇われ弁護士として2年間働いた。
だがインターンから始めた事務所に、ずっといることはできない。ミュラーさんは銀行大手のクレディ・スイスに転職し、チューリヒに戻った。だが1年後、再び中国が自分を呼ぶ声がした。15年、上海のビジネススクール「中欧国際工商学院」のMBA課程に進んだ。
ミュラーさんは「起業家精神やイノベーションに興味がある。中国の経済発展を鑑みても、ここは暮らすのに最も刺激的な場所の一つだ」と話す。
ミュラーさんは中国の文化、歴史に加え、北京語を学ぶようになった。「中国語の漢字の成り立ちにはそれぞれ物語がある。物語を理解すれば、漢字を覚える手助けになる」(ミュラーさん)。すでに中国語検定4級(最高は6級)に合格済みで、現在5級取得に向け勉強中だ。5級は2500種類の漢字を覚えなければならない。

フォトギャラリー上海でMBA取得を目指すスイス人
(写真・ Daniele Mattioli)
ブレットラー姉妹
スイスを飛び出した姉妹夢と冒険を求めてアフリカへ文・Anand Chandrasekhar 写真・Georgina Goodwin
ブレットラー姉妹 アフリカのアーティスト
ブレットラー姉妹 アフリカのアーティスト


「スイスでの生活は管理されすぎていて、生きづらくなった」。ルガーノ出身のダニエラ・ブレットラーさん(52)はそう語り始めた。彼女は今、ケニア北部のラム島で暮らしている。
ダニエラさんの父はティチーノ州アイロロ、母はグラウビュンデン州ポントレジーナの出身。彼女が、愛情に満ちた家庭を離れて陽光あふれる南仏サントロペに移住したのは19歳の時だ。女3人男1人の4人きょうだいの、仲のいい家族だった。しかし、生まれ育った国を出たいというダニエラさんの衝動は、あまりにも強かった。
「スイスは美しい国だ。でも私は、単なる美しさ以上のものを求めていた」とダニエラさん。「スイスでの若者の人生はあまりにも楽だった。私はもっと冒険がしたかったのだ」
だが、華やかなサントロペでの生活も、ダニエラさんを満足させることはできなかった。友人の店を手伝ったり不動産業に関わったりしながら7年が経った頃、彼女の中で旅への衝動が再び高まった。そんな時、美容院で眺めていた旅行誌「パリ・マッチ・ボワイヤージュ」のあるページに目を奪われた。そこにはアフリカゾウに乗る人々の写真があった。それが彼女の人生を変えた。
「昔から自分の夢は、犬よりもゾウを飼うことだった。あの写真を見た時にその夢を思い出したのだ。サントロペにはもう飽き飽きしていたし、変化の機は熟していた」と、ダニエラさんはスイスインフォに語った。
写真について調べてみると、それはボツワナにあるゾウの野生復帰施設で撮られたものだと分かった。ダニエラさんは、さっそく施設の持ち主に手紙を出した。持ち主から彼女に仕事のオファーが届いたのは、それから1年後のことだ。こうして、渡り鳥のように生きる彼女の新しい冒険が始まった。
「仕事の内容は、映画やコマーシャルの撮影、それにゾウのサファリの引率などだった。プロジェクトの目的は、世界中の動物園から問題のあるゾウを引き取り、アフリカの大自然に返すことだ」(ダニエラさん)
姉の決心
その数年後、ダニエラさんの姉であるマリーナ・オリバー・ブレットラーさんも、移住を夢見るようになっていた。しかし彼女の夢は、妹のように冒険を求めるティーンエイジャーの夢とは違っていた。当時34歳の彼女はソフトウェアの会社に勤め、申し分なく暮らしていたのだ。
「残りの人生をこのままで過ごしてはいけない、ある日の朝目が覚めると突然そんな思いに駆られた。スイスは自分には狭すぎる。束縛感があった」と、今年56歳になったマリーナさんは説明する。
マリーナさんは世界旅行を計画した。まずはアフリカに行って妹に会い、それから旅を続けようと考えた。
「私たちは似た者同士、互いによく分かり合える」とダニエラさん。
ヨーロッパを離れてアフリカに渡るという2人の決意を知った家族は、当初はショックを受けた。だが精いっぱいの後押しをしてくれた。
「両親はお金こそくれなかったが、いつまでも私を愛しているし、いつ戻っても部屋はあるよと言ってくれた。その言葉に旅立ちへの勇気をもらった」と、ダニエラさんは振り返る。
「母がもし私たち世代の人間だったら、同じことをしていたかもしれない。父は典型的なスイス人だが、世界を見て回りたいという欲求を理解してくれた」とマリーナさん。
ほかのきょうだいは、この2人ほど冒険的ではなかった。長男はスペインに移ったが、長女はルガーノに残り、幸せな生活を送っている。「長姉は実家から200メートルしか離れていない場所に、夫と3人の子ども、それに犬と暮らしている。実家を離れるかどうかは、人それぞれだ」と、ダニエラさんは考える。

フォトギャラリーケニアの海岸で 心ゆくまで生き抜く人生
(写真・Georgina Goodwin)
アフリカの現実
アフリカの現実


「アフリカの大地に降り立って土か何かの匂いを吸い込んだ途端、もっと長い間滞在したくなってしまった」
マリーナさんは、妹が働いていたゾウの施設から、運営の仕事をしないかと持ちかけられた。それは断るには惜しいチャンスだった。「まずはスイスに帰り、家も車も何もかも売り払った上で、ボツワナに戻った」と、マリーナさんは語る。
しかし、姉妹がボツワナで共に忙しく働く日々は、永遠には続かなかった。
ある時マリーナさんは、2頭のゾウを陸路輸送するという計画の事前調査を行うため、エジプト・カイロを訪れた。そして、そこで人々のひどい貧困状態を目にして衝撃を受ける。「道路脇で暮らすたくさんの人々を見て、ゾウのために大金を集めることに迷いが生じた。この大陸には、ほかに優先すべきことがあるのではと考えた」
ダニエラさんもまた数年後に、失望を味わうことになる。お気に入りのゾウが鎖につながれてしまったのだ。「彼らがゾウを自然に返さなければ、自分はもうここには戻らないと宣言した。それが実行されたのを確認しに戻ったのは2年後。それから3カ月間ゾウを追跡し、無事を見届けてからケニアで新生活を始めた」(ダニエラさん)
再出発
ダニエラさんはナイロビで出会った英国人海洋生物学者と恋に落ちる。しかし、結末はハッピーエンドではなかった。「素晴らしい男性だった。今も心の傷は癒えていない」
つらい恋愛体験を克服するため、ケニアのラム島で地元の漁師を撮影するという仕事を引き受けた。そして、その土地と漁師の世界にすっかり魅了されてしまう。
「ラム島は地球で最も美しい場所。車もディスコもカジノもなく、まだ汚されていない。ここでは、いつも恋をしている気持ちだ」
しかし漁師たちの暮らしは厳しい。トロール漁船との競合や雨季の危険な海での漁など、生計を立てていくのは大変だ。ある時、アリ・ラムという名の漁師が職を求めてダニエラさんの元にやって来た。どうしたら彼の力になれるだろうと考えるうちに、あるユニークなアイディアが浮かんだ。「漁船の帆に使われている素材に注目した。その帆布に大きなハートを描き、『Love Again Whatever Forever』という文字を足して、額に入れてみた」
そうしてできた作品を友人の店に展示するよう頼んだところ、1時間も経たないうちに180ユーロ(約2万円)で買い手がついたのである。ダニエラさんは漁師たちの協力を得て、さらに製作を続けた。それらの売り上げは好調で、やがてダニエラさんは、リサイクル帆布を使ったクラフトワークやバッグの販売を行う会社を設立する。
ダニエラさんは、ブランド名を「Alilamu(アリラム)」とした。あの漁師から取った名前だ。彼女の会社では現在30名がフルタイムで働く。ラムさんもその一員で、今では取締役の地位にある。「ラムさんは私の精神的な支えであり、友人、兄弟、そして最大の支援者だ」と、ダニエラさん。
職を求めてダニエラさんを訪ねて以来、ラムさんの暮らしも変わった。「家族のために小さな家を建て、子どもたちを学校に通わせることができた。漁師をしていた頃は、借りていた1部屋の家賃を払うのもやっとだった」(ラムさん)

フォトギャラリー夢を実現 タンザニアのマサイ族とともに
(写真・Georgina Goodwin)
タンザニアのアート
タンザニアのアート


マリーナさんは、古参のアフリカ・エキスパートであるポール・オリヴァーさんと出会い、結婚する。ポールさんは、タンザニア北部のアルーシャ近郊で人気のサファリキャンプを経営しており、彼女も運営に参加した。だが、その仕事に心から打ち込めないでいた折、新しいチャンスが訪れた。ミラノでNGOを主宰する友人に、面白い仕事を紹介されたのだ。
「仕事内容は、マサイ女性の作るビーズアクセサリーのマーケティングだった。彼女たちに収入源を与えるためのプロジェクトだ。最終的には事業を女性たち自身に任せるという条件付きで、引き受けることを決めた」
2年後、このプロジェクトからタンザニア・マサイ・ウィメン・アートという名の独立した会社が生まれた。約200人のマサイ族の女性が働いている。彼女たちはグループ収入の10%を積み立て、小屋の修理など地域の発展に役立てている。
「マサイ女性の約99%は読み書きもできず貧困の中で暮らしている。自分にはそんな生活を一変させることはできないが、少なくともビーズ工芸が売れることで、自信や自尊心が育つはず」(マリーナさん)
マサイ女性の生活は過酷だ。食事作りのために薪を集め、水を運び、その上家畜の世話もしなければならない。地域社会の決定において女性の意見は考慮されない。肉体的な虐待を受けることも珍しくない。
マリーナさんは、1年がかりで彼女たちの信頼を得た。いつの日か女性たちにアクセサリービジネスを任せ、自分は一線から退きたいと思っている。次のプロジェクトも待っている。身体的障害を持った子どもたちに乗馬セラピーを提供するための施設を作るというものだ。
「マリーナはとても強い人だ。自分のやっていることを愛し、周囲を励ましてくれる。マサイの女性たちは仕事の依頼が来るたびに、大喜びしている」と語るのは、4月まで店舗販売を担当していたマーガレット・ガブリエルさんだ。
規則だらけのスイス
1年に1度里帰りはするものの、姉妹の心の中でスイスは遠い存在となった。「スイスはまるでリゾート地。すべてが清潔で秩序だっている」と、ダニエラさんは感じる。
彼女は、スイスではスイスの食べ物を食べ、山歩きをし、大手スーパーのミグロで買い物をして休暇を過ごす。「自分自身、もうスイス人というよりスワヒリ族の感覚だ。人が時間を守ってくれればうれしいが、遅れたとしてもあまり気にならない」
ダニエラさんはラム島の地域社会にすっかり溶け込んだ。3歳から18歳までの地元の子どもたち4人を養子に迎え、「カリラ」という現地名まで与えられた。
「ラム島は美しく平和で、健康や心と精神のためにはとてもいい。毎朝日の出を見るために浜辺まで歩き、日没も見に行く。その一方で、電車に乗って仕事に行けば、にぎやかな場所にも出られる」
スイスのチョコレートに未練は残るが、もうスイスに住むことはできないとダニエラさんは言う。自分が過度に管理されている気分になるからだ。
「スイスには禁止や注意の看板があちこちに立っている。ラム島では、周囲に危険が存在しても人々は自由に行動できる」
その危険には、イスラム武装勢力のアルシャバブも含まれる。ラム島近くの地域でこれまで数度の襲撃が行われた。アルシャバブが拠点とするソマリアはここから遠くない。
「島での襲撃はまだないが、数カ月前に襲撃予告があって以来、道路や海水浴場、大型ホテルなどで保安部隊を見かけるようになった」と、先述のラムさんは証言する。
彼はまた、4人の養子を迎えるなどした、ダニエラさんが抱える責任の重さも気にかけている。「彼女は広い心の持ち主だ。だが、養女が病気になった時もそうだったが、独り身の彼女には誰かの助けが必要なことがある」
ボーマと開放的空間
姉マリーナさんも友人の農場内にモンゴル風のテントを構え、馬とロバを1頭ずつ、そして犬2匹と共に暮らすなど、典型的なスイス人とはかけ離れた生活を送る。
「スイスにいると閉所恐怖症になってしまいそうだ。私はここの開かれた空間が好きだ。山、森、そしてサバンナが」とマリーナさんは言う。
仕事の性質上、彼女の毎日に決まった時間割はない。これはタンザニアでは一般的なことでもある。想定外の出来事が定期的に起こるのだ。物事が比較的スムーズに進行している日であれば、日課としてやりたいことがある。「乗馬で1日をスタートする。そのあとアルーシャにある店とオフィスに向かう。夕方帰宅したら犬と長い散歩に出て、日が沈むのを眺める。時には友人たちと飲んだり、夕食を共にしたりする」(マリーナさん)
ボツワナと違い、ここにはハイエナやジャッカルなど小型肉食動物がいるだけで、ライオンやヒョウといった危険な野生動物はいない。そのため、マリーナさんは自由に歩き回ることができる。近辺にはマサイ族の居住区でもあり、ボーマと呼ばれる伝統的な掘っ建て小屋が点在している。週末になるとマリーナさんは自転車に乗ってマサイ族の村を訪れ、収入を増やす方法について住民と語り合う。
しかしアフリカには別の顔もある。「アフリカに住んでいるとよく人に羨ましがられるが、ここではてこずることも多い。インフラは不安定だし、官僚社会で腐敗も多い」
夫と離れて暮らしているマリーナさんは、数人の友人と会う以外は孤独だ。しかし、もはやスイスに戻れるとは思えない。「スイスは小さな島のようなもので、それが人々の考え方に影響している。思考が国境で止まってしまうのだ」
だが、雪やスキーは恋しいし、スイス人の秩序だったやり方も懐かしく思うようだ。「途上国で先進国向けの商品を作るのはとても難しい。タンザニア人のスローなペースには、たまにイライラさせられることもある」とマリーナさんは言う。
将来の不安?
前出の元仕事仲間だったガブリエルさんは、マリーナさんが仕事や活動に打ち込みすぎると心配する。マリーナさんが心血を注いだ事業の将来も気がかりだ。
「年を取って視力が落ち、ビーズ作業が難しくなってきた女性たちもいる。若い少女たちを対象としたプロジェクトを立ち上げて、事業を次世代へ引き継がなければ」と、ガブリエルさんは考えている。
膨大な仕事量、そして200人のマサイ女性に対する責任を抱えながらも、マリーナさんに後悔の念はない。「私は今まさに自分の夢を生きている。大金こそ持たないが、必要なものはすべて揃っており、とても安らかな気持ちでいられる。これこそが、自分が人生で求めていたものだ」
移住を夢見るスイス人に、ダニエラさんがアドバイスしたいことがある。「友人たちは私のことを勇敢だと言う。なぜだろう。一生スイスで過ごす方がよほど勇気が要るのではないだろうか。不安がったりお金のことを心配したりするよりも、自分の心のままに行動すればいい。心を開いていれば、何事もかなえられるから」
(英語からの翻訳・フュレマン直美 編集・スイスインフォ)

シルヴィア・ブルッガー
アラスカへの移住過酷な犬ぞりレースに挑戦、あるスイス人女性の物語文・Philipp Meier 写真・Trent Grasse
シルヴィア・ブルッガー アラスカで冒険
シルヴィア・ブルッガー アラスカで冒険


「親愛なるフィリップ、短い自伝を送ります。こういうものを書くのは初めてで、どこから始めていいのか分からないけれど」
これが、ブルッガーさんが長い手紙のようにしたためた、移住についての物語の書き出しだ。ブルッガーさんとは、今の時代よくあるようにフェイスブック上で知り合った。
この外部リンク先サイトのコンテンツは、当該リンク先サイトの管理者にあるため、アクセシビリティに対応していない可能性があります。
フェイスブック上で筆者が行った呼びかけに、ブルッガーさん本人が返事をくれたのは非常に幸運だった。彼女は、同じ交通専門高等学校に通っていた仲間から筆者の投稿について知らされると、当然のようにいわゆる「ユーザー生成コンテンツ」を作り、自身について語ってくれた。筆者は途中数回、そして最後に一度、少し掘り下げた質問をするにとどめた。
ここからは、ブルッガーさんとのやり取りをそのまま載せたものだ。ブルッガーさんの物語は次のような書き出しで始まった。
私は、1974年、ツーク州ハームで生まれ育った。私には4人のきょうだいがいる。マックスは私の双子のきょうだいで、ほかの3人は4歳年上と8歳年上だ(姉たちも双子)。
私は、子どもの頃から多くのヨーロッパの国々を訪れた。祖父母が北ドイツに住み、両親がアイスランド種の馬を数頭持っていたので、姉たちと毎年のように馬術大会のため外国に遠征した。
中学を卒業すると、私はルツェルンにある交通専門高等学校に入学した。卒業後はスイス航空(当時)に就職するつもりだった。しかし、就職前に冒険をしたくなった。オーストラリアのパースに行って語学研修を受けたあと、友人とオーストラリア中を回った。その時、私たちはたったの18歳だった。
その後は、自分の将来に集中した。チューリヒにあるカールトン・エリート・ホテルで事務職の職業訓練を修了すると、サン・モリッツのバドルッツ・パレス・ホテルでシーズンスタッフとして働くことになった。
パレスホテルで人生のために学んだことは?
ちょっと考えさせて。ぼんやりとしか思い出せない…。きっと毎晩遊びに出てビールを飲みすぎたせいかもしれない :-)
一般的にスイスで学べたと思うのは、ここアメリカでは少し欠けていると感じる自制心と責任感。この二つは仕事で成功するためになくてはならない。例えば私が我慢できないのが、アメリカの訴訟ビジネス。マクドナルドでコーヒーを頼んだ客が、舌をやけどしたからといって訴訟を起こし、100万ドル(約1億600万円)もの賠償金を手に入れる。意味が分からない。でも今やこれが当たり前になってしまった。公共心はもう必要とされていないようだ。
1997年のカナダ旅行で、アンカレッジから来たウィリスという一家と知り合った。彼らはアイスランド種の馬だけでなく、犬ぞりを引く犬も飼っていた。バーニーとジャネットのウィリス夫妻は、その場で私を数週間のアラスカ滞在に招いてくれた。それが私の初めてのアラスカ行きとなった。
パレスホテルで最後のシーズンを終えると、1999年アラスカに移住、同じ年にアンディ(バーニーとジャネットの長男)と結婚した。
2001年に、アンディと私は自分たちのロッジを作り上げた。家付きの土地を競売で買い、掃除と片付け、修理とリノベーションに1年を費やした。
子どもの頃、釣りと狩りをするためのロッジを持つことが夢だったが、まさかそれが実現するとは思ってもみなかった。それは冒険に満ちた生活だった。自分たちのロッジで夏は釣り、春秋は狩り、そして冬にはそり犬たちを訓練した。
アンディと彼の家族は、世界的に有名なアイディタロッド犬ぞりレースにとても熱心に関わっていた。男たちは皆、それぞれ違う年に参加していた。07年と08年、私たちは特に優秀なそり犬チームをまとめ上げることができた。そしてついに、私がこの1千マイル(約1600キロメートル)の犬ぞりレースに参加することになった。私はこのレースに参加した最初のスイス人女性となった。

フォトギャラリー私のアラスカでの暮らし
(写真・Trent Grasse)
そり犬とレースの何に魅了された?
そり犬とレースの何に魅了された?


そり犬はもちろん普通の飼い犬とは違って労働のための犬。何世代も前から牽引動物として飼われ、労働に用いられている。
もちろん、犬たちと一緒に外に出るのは楽しかった。30マイルとか40マイルの距離をね :)
私は活動的で、いろんなことに挑戦するのが好き。だから犬たちを趣味として飼うだけでなく、わりあいすぐに、短距離のレース(200マイルから300マイル)にも参加するようになった。レースのために20匹ほどの犬からなるチームを作り、アイディタロッド犬ぞりレースへの参加にも備えた。全ての犬を自分で育て、夫と一緒に訓練した。
そり犬たちと走りに行くと、いろんな感情を味わえる。冒険的だし時には危険でもある。うまく行かないことも多い。原野では道に迷いやすく、犬が攻撃的なヘラジカに襲われ怪我をしたり、殺されたりすることもある。そしてもちろん寒さ。マイナス30度から40度は珍しくない。11月から1月までは日がとても短く(午前10時から午後3時)、朝の8時から夕方6時まで訓練するのはかなり過酷だ。
でも、つらい訓練も報われる!冬の終わり(2月と3月)にはまた日が長くなり、普通の年なら雪の状態も理想的で気温も快適(マイナス10度から20度)。そんな条件の時に、12匹のよく訓練された犬たちと「ラン」に行くほど素晴らしいことはない。あたりは静まりかえっていて犬たちの呼吸以外何も聞こえない!感動で本当に鳥肌が立つほど。そして夜は戸外にいれば、オーロラも頻繁に楽しめる。
そしてもちろん自分にとって一番の挑戦は、犬ぞりレースへの参加。特に、伝説的とも言えるアイディタロッドのレース!1千マイルというのはとても長い距離だ。優勝者のタイムは、天候とルートの状態によるが、およそ9日。完走できれば苦労は報われる。
私は1千マイルの完走に10日かかった。詳細データについてはwww.iditarod.comを参照してほしい(07年と08年の「アーカイブ」で「Silvia Willis」を検索のこと)。
07年が私のデビューの年(いわゆる「ルーキーイヤー」)。毎日が冒険で、ルーキーたるがゆえに何が起こるか予測できない。天候はそれほど悪くなかった。ただ、かなり寒さの厳しい年だったので、多くの参加者(犬と人間)が凍傷と闘っていた。私もゴールに着いた時は顔中が腫れ上がっていた。左手もひどい炎症を起こしていたため、レース中のチェックポイントで救急手術を受けることになった。大会ボランティアの看護師(医師ではない!)が小さな救急セットを持っていた。
こういった生活スタイルは、長い目で見ると結婚生活への負担が多すぎた。アンディと私はしばらくして離婚した。私はその後「原野」から街に移り、今は「文明的な」生活を送っている。犬ぞりレースはとても楽しかった。今でも恋しく思う。でも犬の世話は本当に大変だった。毎日エサをやらなければならないので休暇にも行けなかった。トレーニングが休みになる夏(暑すぎるため)は、ロッジの方が繁忙期に入った。
私は今、K&Lディストリビューターズという会社でビール販売チームのリーダーとして働き、6人の部下がいる。K&Lディストリビューターズという会社は、アラスカでアルコール飲料の販売をしていて、私はアンカレッジ、ワシラ、パーマーの3市にある約80の店舗のビール販売部門の責任者。
スイスで懐かしく思うものは?
たくさんある。スイスの公共交通網はアラスカとは比べることもできない。アラスカはあまりにも広すぎて公共交通網を作るのは資金的に無理。それから、たくさんのハイキングルート。アラスカには自然や山はたっぷりあるけれど、人里離れた場所にあって危険(野生動物)もある。私はスイス人としてチョコレートにもうるさいから、スイスからアラスカに帰る時はカバンというカバンにいっぱいチョコレートを詰め込む。
普段からアラスカとスイスを比べては、人生の残りを過ごすにはどちらの国がいいかと考えている。スイスに戻って家族の側にいるべきだろうか、経済や公共医療はどちらが優れているかなど。「正解」にたどり着くまでの道のりは長い。どちらの国(アメリカとスイス)にも長所と短所があり、てんびんにかけるのは難しい。
自分の自由と夢を実現するのはアメリカの方が簡単だ。私がアメリカと言う時は、アラスカのことを指している。ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴなどの大都市ではとても暮らせない。アラスカはスイスに似ている。私は特に山が好きだ。
スイスはとても規制が多い気がする。あまりにも多くのことが国家に決められている。スイスは比較的小さな国で人口密度も高い。里帰りすると時々閉所恐怖症のようになることがある。
スイスの友人や親戚との付き合いは?
今はもうほとんどフェイスブックだけの付き合い。でもとても楽しい。こんな方法で元同級生たちの近況に触れられるのは素晴らしい。フェイスブックがなければ、まったくついていけてなかっただろう。Googleハングアウト(グループチャット)を使って定期的に姉たちや父とも会話している。2カ月に一度ほど、日曜の朝にオンラインで集まる。
アメリカに来て17年。アメリカは完璧ではないけれど、自分にとっては夢を簡単にかなえることができる国。どうしたら自分の思っていることをもっとよく言い表せるのだろう。うまい言葉が見つからない。スイスでの私の人生には決められたコースがあった。学校、職業訓練、就職。そのあとは、定年後のために貯金をしながらずっと働き続ける。
私が心配しているのは、アメリカよりもヨーロッパの政治や経済。でも今は世界中が変革のただ中にある。どこに住んでいてもその影響はある。アラスカは自然資源に依存していて、巨額の財政赤字と闘っている。人々は不安を感じている。将来どうなるか分からない。私はヨーロッパ情勢も心配なので、スイスが欧州連合(EU)に加盟しなかったのはよかったと思う。それでもスイスはヨーロッパにあってEUの国々に囲まれ、その影響を受けているのだけれど。
私はスイスが嫌いだから離れたわけではない。自分の視野を広げる機会があったから、それを利用したのだ。私は自分のルーツを誇りに思っているし、母国を愛している。スイスへの里帰りも楽しみにしている。でも毎回、スイス滞在も終わりになると、アラスカにまた「帰国」できるのをうれしく思う。
(独語からの翻訳・フュレマン直美 編集・スイスインフォ)

ホステットラー夫妻
闘いの人生快適なベルナーオーバーラントからパラグアイの原生林の中へ文・Marcela Aguila 写真・Rodrigo Muñoz
ホステットラー夫妻 パラグアイで原始林の保護活動
ホステットラー夫妻 パラグアイで原始林の保護活動


「スイスに戻りたいかって?答えはノーよ」。クリスティーンさんはきっぱりと答える。「ここでは私たちは自由で、何かを生み出すこともできる。スイスではそれを想像することすら許されていない」
2人は「自由」を大いに謳歌(おうか)した。自然保護団体を設立し、エコツーリズムを促進するプログラムを作り、自分たちの故郷にちなみ「ニュー・ガームバッハ」と名づけた有機農場も作った。ホステットラー夫妻はその農場で筆者を出迎え、「五つ目のスイス」と呼ばれる在外スイス人として暮らすパラグアイでの、これまでの36年間の体験を話してくれた。
2人は、故郷へのノスタルジー、家族、友人、文化、それから「清潔で整然とした」スイス社会について語った。だが、2人にとってはイタプア県アルト・ベラにハンスさんが自分の手で建てたこの家が、自分たちの居場所だと強調する。彼の家はサン・ラファエル国立公園に隣接している。
危険な契約
自宅が国立公園に隣接していることで多くのことが起こった。ホステットラーさんの生活は、地球上で最も豊かで最も危機にさらされている生態系を持つ、大西洋岸森林地帯にあるパラグアイの原始林の保護活動と密接な関わり合いを持つ。
危険な目にもあった。忘れもしない2008年のある日曜日。「その日はサッカーがあって、私は独りで家にいた。何か物音がしたので外に出てみると、目出し帽をかぶり、私に38口径の銃口を向けた男と鉢合わせをした」とクリスティーンさんは語る。神様が守ってくれたのか男の手元が狂ったのかは分からないが、放たれた銃弾は運よくクリスティーンさんをそれた。
ハンスさんも危機一髪だったことがある。森林の不法開発や不正な耕作、火事などの監視のために森の上空を小型機で巡回していたとき、地上から誰かが機体に向かって発砲した。「彼らは、私たちを殺せば(森林保護者との)戦いが終わると思っていた。だが、森林を守ろうとする人は、私たちだけではなく何人もいる」と、クリスティーンさんは誇らしげに語った。
寒いベルナーオーバーラント
ここで、彼らの冒険の出発点となった70年代にさかのぼってみよう。ホステットラー家は、自治体ルーシェッグのガームバッハで静かな生活を送っていた。いや、静か過ぎたのかもしれない。大西洋の向こう側に土地を買うチャンスがあると聞いたとき、夫妻は「やってみよう」と思った。
親戚のサポートもあって、「新世界」の南米に250ヘクタールの土地を購入した。夫妻にとってはまさに新しい世界だったが、どちらかというと「時代遅れの」新世界だった。クリスティーンさんは、「まるで50年前にタイムスリップしたようだった」と、インフラなど全く存在しない「冷酷な楽園」に着いたときのことを振り返る。スイスの生活は、寒くて単調だったが快適で安全だった。
クリスティーンさんはまだ小さかった長女のブリギッテさんを抱いて、1979年2月にパラグアイに来た。夫のハンスさんは6カ月前に現地に入り、文字通り「地ならし」をした。かつて船員だったハンスさんは、家族を迎える木造の家を建てるために木を切り倒し、雑草を刈り取らなければならなかった。
ハンスさんはとても手先が器用だ。家を何度も補強し、発電のためにダムも造った。大型農機具のメンテナンスもすれば、郵送で受け取った超軽量飛行機の部品を組み立てて超小型飛行機の「ルーシー」も作った。

フォトギャラリー私のアラスカでの暮らし
(写真・Trent Grasse)
長期戦
長期戦


それでも次第に農業、特に牛乳で収入が得られるようになった。クリスティーンさんはスイスではなくパラグアイでチーズ作りを学び、ブリギッテさんには妹のテレザさんと弟のペドロさんができた。大豆の有機栽培も軌道に乗り、ホステットラー夫妻は環境保護に取り組むようになった。
夫妻は1997年に自然保護区の保全に努める団体「プロ・コサラ(Pro Cosara)」を設立し、世界自然保護基金(WWF)の支援で小型飛行機も購入した。プロ・コサラは1922年に自然保護区に指定された一帯を監視し、また保護区内でパラグアイ政府が買い取らなかった私有地の購入を試みている。
私有地の購入に成功すれば、7万3千ヘクタールの「エコロジー・パーク」を作ることができるのだが、この土地は大豆などの粗放農業や不法なプランテーション、違法森林伐採などに脅かされているのが現状だ。
新たな挑戦
クリスティーンさんたちは、団体の活動を安定させるために休みなく働き、今では国際的ネットワークにも参加し、支援を受けるまでになった。保護区の生態系調査を実施し、人々の自然保護に対する関心を高め持続可能な保護活動を展開するために、環境教育などにも力を入れている。
クリスティーンさんは今年の2月にプロ・コサラ代表を降りたが、現在でも顧問として活動を続けている。それだけではなく、エコツーリズムという新しいプロジェクトにも着手した。先ごろは、米国から70人の学生が訪れ、自然保護区に生息する70種類近い鳥が観察された。
パラグアイはまさに楽園。だが、故郷ベルナーオーバーラントの風景もまた牧歌的な楽園だ。パラグアイへの移住は、果たして正しい決断だったのか?「最良の選択」と、クリスティーンさんは即座に答える。自由であることに加え、子どもたちが自然に触れ、自然を尊重しながら成長できることに満足していると言った。
心の中には常にスイスが
家族、農場、文化、環境保護への取り組み。充実した人生にはそれで十分だった。だが、彼らが生まれた故郷スイスのことは、片時も心から離れることはなかった。
2人の娘は現在スイスに住んでおり、夫妻も定期的にスイスを訪れる。パラグアイでも、スイス人の友人たちが主催する活動に参加し、クリスティーンさんは現地に住むスイス人定年退職者が、スイスから年金を受け取れるように5年間ボランティアとして働いた。
移住から40年が経って、クリスティーンさんは祖国をどう見ているのだろうか?「劇的に変わった。私の思い出の中のスイスとは全く違う。両親の世代は何年も外国人労働者とともに働いていたが、彼らには滞在権があり、彼らの文化をスイスに押し付けてくることもなかった。だが今日の状況は違うようだ。スイスがそのアイデンティティーを失うのではないかと恐れている」(クリスティーンさん)
では、スイスを離れようとしている人にはどのようなアドバイスをするのだろう?「最終的な決定を下す前に、その国に行って最低でも3カ月は暮らしてみることだ。実際に住んでみる前にコンテナで全ての家財道具を送り、貯金をはたき、あとから自分が想像していた生活と違うことが分かって後悔する人がいる」
ホステットラー夫妻は当時まだ若かったにもかかわらず、スイスを離れるときに全てを手放すことはなかった。家財道具は長い間ルーシェッグに残したままにしておいた。最後の荷物が着いたのは、つい最近のことだった。ホステットラー夫妻は移住を決意したときに、背水の陣を敷いたわけではなかった。
(仏語からの翻訳&編集・由比かおり)

ブルーノ・マンサー
熱帯雨林に生きる「簡素な生き方に戻ろう」文・Ruedi Suter 写真・Bruno Manser Fund
ブルーノ・マンサー マレーシアで殉職
ブルーノ・マンサー マレーシアで殉職


「マレーシア政府や木材企業がマンサー氏の口を封じるつもりだったことは裏付けされている」。03年末、氏の失踪に関する裁判手続きの際、バーゼル民事裁判所はそう説明している。バーゼルで育ったマンサー氏は生きることをこよなく愛していた。しかし問題に背を向け、破壊や略奪を容認することができなかった。そして原住民の犠牲や自然の略奪の上に成り立つ、自分が育った産業社会を受け入れることはできなかった。そんな彼は、禁欲をもって飽和状態の現代社会に対抗した。氏の人生は、ひたすら簡素な生き方に戻る過激な道だったと言える。知能、創造力、そして頑固さとユーモアを持って、できる限り現代の生活様式を拒んだのだ。
マンサー氏は学業を諦めてチーズ職人になり、羊飼いになった。11年も山で暮らした彼はこう言う。「毎日の生活に必要な知識を全て身につけたかった」。そしてその知識を実際に生かすために、太古の昔から狩りや採集で暮らす民族を探した。だが技術化の進んだ欧州では、そういった民族は既に消滅していた。そのため、氏は1984年、マレーシア領の一つであるボルネオ島のサラワク州へ旅立った。そこで勇敢に原生林を探索し、完全な移動民族として今もなお森に生きるプナン族300世帯に出会った。
プナン族はこの変わり者を仲間として受け入れた。そこで彼は衣類、救急箱、歯磨き粉、靴など、自分の所持品を全て捨てた。ただし近眼だったため、眼鏡だけは取っておくことにした。プナン族のように裸足で歩く生活を試みたが、初めは慣れず、いつも足が傷だらけで、毎回ナイフでとげを抜かなくてはならなかった。やがて痛みに耐えることを覚えた。原生林の中でプナン族と同じ生活をするには、痛みに慣れるしかなかったのだ。そして、いつしか裸足の生活が苦にならなくなった。現代人である彼が、もう靴にしばられないでも生きていける。それは正に、自分自身に対する勝利だった。
同じ仲間に
彼は瞬く間に周囲からも認められるようになった。一切妥協せず、プナン族と全く同じ生活を営んだ。裸足で歩き、衣類をまとわない暮らし。空腹や湿度、昆虫、ヒルに耐え、皮膚病とマラリアに悩まされる毎日。そしてこの眼鏡をかけた男は、いつしかプナン族と変わらない森の住民になっていた。マチェテ(山刀)で巧みに茂みをかき分け原生林を進み、プナン族と同じようにしゃがんで休み、氾濫する川を泳いで渡り、夜は木の上に寝床を作って眠った。
この移動民族の簡素な生き方が、マンサー氏はとても気に入っていた。まるで自分の前世の家族と再会したようだった。狭く、排気ガスと騒音に溢れるスイスにはもう戻るつもりはなかった。種の多様性を破壊し、次第に自然な生き方から遠ざかり、技術や金儲けや娯楽産業に人生の意味を追い求める現代人。そして結局は行き先を見失い、ますます不幸せになっていく人間の元に帰る気持ちは毛頭なかった。
自分はこの質素な、温かい心を持つ人々と共に生き、共に苦しみ、喜び、命を育む原生林で幸せに暮らすのだ。
やがて彼はプナン族にとっての仲間「ラキ・プナン」になった。野獣を知り尽くし、投網で魚を捕まえ、吹き矢や毒矢、そして槍と鉄砲で熊や猿、猪、鹿、鳥を狩り、野生の果実を集め、ヤシの幹中に蓄積されるサゴでん粉を採集した。言葉を学び、観察したことを書きとめ、人間、動物、植物について数えきれないほどの記録を残した。

フォトギャラリー熱帯雨林・人権保護活動家
(写真・Bruno Manser Fonds)
文明の侵略
文明の侵略


もしかすると彼は、この澄んだ水と動植物に溢れる見事な森が、いつの日か破壊されてしまうことを薄々感じていたのかもしれない。
事実、既に原生林のあちこちで木材企業による乱伐が進んでいた。木材企業には政府という強い後ろ盾があった。政府は森の果実を食べて平和に暮らす原住民がこの地に生きる権利と、深刻になりつつある彼らの窮状を無視した。サラワク州の首都クチンにいる政治家にとって、熱帯雨林は単なるセルフサービスの店に過ぎなかったのだ。産業社会の消費者が求める屋根の梁、家具、高級ヨット、窓枠やホウキの柄を作るために、大木から取る良質な硬材が次々と輸出されていった。
「国家の敵」ナンバーワンに
そして森に響く鋭いチェーンソーの切断音を耳にした時から、マンサー氏にとって楽園からの追放劇が始まった。プナン族に助けを求められた彼は、原住民と共にバリケードでブルドーザーに対抗した。彼は突然、文明に対するプナン族の平和的な抵抗を助ける戦略家に様変わりした。それはかつて自分が背を向けた文明、そして権利をふりかざし、兵士を送り込み森の民族の生活空間を破壊するコンツェルンと国家権力への抵抗だった。こうして国家の敵・ナンバーワンと化した彼は、まるで獣のように追われ、銃で狙われる存在になった。
やがてマスコミが訪れ、この変わり者は「勇敢な熱帯雨林保護活動家」として脚光を浴びることになる。そしてこの「白いターザン」は世界中の報道機関にとってプナン族の代弁者となった。謙虚で、もの静かな彼の正直な言葉に、世界中の人々が耳を傾けた。こうして抵抗の立て役者であるマンサー氏は、熱帯雨林の乱伐に対する反逆のシンボルと化したのだった。
「プナン族の生活空間が安い木材の犠牲になっている事実に触発され、私は1990年、スイスへ戻る決心をした。この文明社会に『我々の森を破壊してあなたたちの家を建てないで』という彼らの叫びを伝えるために」。バーゼルでは人権活動家のロジャー・グラーフ氏の援助で「ブルーノ・マンサー基金(BMF)」を設立。今では熱帯雨林の保護には欠かせない機関へと発展した。「産業国全ての消費者が熱帯樹の使用を止めること」が基金の目標だ。
基金はこの狩猟民族と森の共生関係を明らかにし、「森の死は、この民族の死を意味する」と訴えた。口調こそ穏やかだったが、欧州連合(EU)、国連、国際熱帯木材機関(ITTO)といった国際的な組織に絶望的な事実を説明し、プナン族の苦境を訴えかけた。スイス滞在中、マンサー氏はできる限り質素な生活をしながら、四六時中働き、各地を訪れた。そしてボルネオ島ではプナン族に対する攻撃に抵抗して戦った。プナン族に残された時間はわずかだと感じた彼は、ますます過激な行動に出るようになっていった。
消息が途絶える
マンサー氏は「木材と木材製品の出産国明記の義務化」を求めスイスでハンガーストライキを決行、物議を醸した。だがそんな努力もむなしく、「飽和社会の人間は空腹者の気持ちを理解しようとしなかった」(マンサー氏)。サラワクの熱帯雨林はますます消滅し、動物は追い散らされるか乱獲された。それに伴い、かつて健全に機能していた森の民族、プナン族の困窮化も進んだ。1996年には、既に原生林の7割が破壊されていた。問題に目を向けさせようと、欧州とサラワクで無謀な抗議行動に出たマンサー氏だったが、その努力が報われることはなかった。そして2000年に再びボルネオへ旅立った彼は、そこで永遠に帰らぬ人となった。
氏は暗殺され、跡形もなく抹消されたのだろうか?恐らくそれが最も有力な死因と思われるが、事故死や自殺の形跡が見当たらないのと同じく、暗殺の証拠も全くない。彼の失踪は今も謎に包まれたままだ。ブルーノの帰りを待つことはもうやめた家族や友人。だが彼は心の中に生き続けている。時々、ふと彼の力強い声が聞こえるような気がするという。「本当に意味があるのは、行動だけだ。それは君も同じことだよ」
リュディ・ズーター、「ブルーノ・マンサー 森の声」著者
(独語からの翻訳・シュミット一恵 編集・スイスインフォ)

関連記事
在外スイス人12人に聞いた 「遠い空から眺めるスイスはどんな国?」
多くのスイス人が、世界のさまざまな国で暮らしている。スイスインフォはインスタグラムを通じて彼らにコンタクトを取り、母国スイスから遠く離れて生活する中で、スイスに対する見方はどのように変化していくのかを聞いた。
国外在住のスイス人76万人に 日本は1687人
国外に居住するスイス人は昨年末、76万200人(前年比1.1%増)に達した。 ほとんどが近隣諸国と米国に住む。日本には1687人のスイス人が居住する。
最後の遊牧民プナン族と暮らしたスイス人写真家
写真家トーマス・ヴュートリヒさんは、ボルネオ島北部のマレーシア・サラワク州の熱帯雨林で先住民族のプナン族(ペナン族)と生活し、彼らの暮らしぶりをカメラに収めた。吹き矢を使った狩猟から熱帯雨林の伐採まで、存亡の危機にあるプナン族の日常を写真で伝える一方、「自分は第二のブルーノ・マンサーではない」と語る。
在外スイス人の最高齢男性が死去 110歳
在外スイス人男性で最高齢のルドルフ・ブクセルさんが2月、米国ミシガン州で死去した。110歳だった。ブクセルさんは帝政ロシアのスイス人集落で生まれ、晩年は米国で質素な生活を送った。




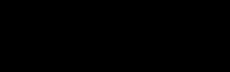






















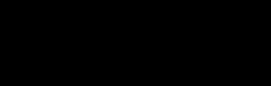 スイスという「黄金の鳥かご」を抜け出したスイス人たち
スイスという「黄金の鳥かご」を抜け出したスイス人たち
 成長し続ける中国に、将来の光を見出す
成長し続ける中国に、将来の光を見出す
 ニクラウス・ミュラー
ニクラウス・ミュラー
 上海でMBA取得を目指すスイス人
上海でMBA取得を目指すスイス人
 黄金のセーフティーネット
黄金のセーフティーネット
 夢と冒険を求めてアフリカへ
夢と冒険を求めてアフリカへ
 ブレットラー姉妹
ブレットラー姉妹
 ケニアの海岸で 心ゆくまで生き抜く人生
ケニアの海岸で 心ゆくまで生き抜く人生
 アフリカの現実
アフリカの現実
 夢を実現 タンザニアのマサイ族とともに
夢を実現 タンザニアのマサイ族とともに
 タンザニアのアート
タンザニアのアート
 過酷な犬ぞりレースに挑戦、あるスイス人女性の物語
過酷な犬ぞりレースに挑戦、あるスイス人女性の物語
 シルヴィア・ブルッガー
シルヴィア・ブルッガー
 私のアラスカでの暮らし
私のアラスカでの暮らし
 そり犬とレースの何に魅了された?
そり犬とレースの何に魅了された?
 快適なベルナーオーバーラントからパラグアイの原生林の中へ
快適なベルナーオーバーラントからパラグアイの原生林の中へ
 ホステットラー夫妻
ホステットラー夫妻
 私のアラスカでの暮らし
私のアラスカでの暮らし
 長期戦
長期戦
 「簡素な生き方に戻ろう」
「簡素な生き方に戻ろう」
 ブルーノ・マンサー
ブルーノ・マンサー
 熱帯雨林・人権保護活動家
熱帯雨林・人権保護活動家
 文明の侵略
文明の侵略
 雑談
雑談
 ちょっとひと休み
ちょっとひと休み
 熟考の時間
熟考の時間
 マーケットで買い物
マーケットで買い物
 友達と連絡を取り合うのも大事
友達と連絡を取り合うのも大事
 マリンディにあるダニエラさんの家へと続く道
マリンディにあるダニエラさんの家へと続く道
 スイスからは脱出したが、デスクワークから脱出する術はなさそうだ
スイスからは脱出したが、デスクワークから脱出する術はなさそうだ
 従業員と、養子に迎えた4人の子どもたちと夕食を共にするダニエラさん
従業員と、養子に迎えた4人の子どもたちと夕食を共にするダニエラさん
 子どもたちを学校へ迎えに行く途中
子どもたちを学校へ迎えに行く途中
 マリンディにある自宅はワークショップの場所も兼ねる
マリンディにある自宅はワークショップの場所も兼ねる
 放課後は子どもたちと充実した時間を過ごすように心掛けている
放課後は子どもたちと充実した時間を過ごすように心掛けている
 リサイクル帆布がお洒落なバッグへと変わる
リサイクル帆布がお洒落なバッグへと変わる
 お気に入りのモチーフ、ハートをメインにバッグを製作するダニエラさん
お気に入りのモチーフ、ハートをメインにバッグを製作するダニエラさん
 アリラム・ワークショップは常に活気に溢れている
アリラム・ワークショップは常に活気に溢れている
 助手のシュエブさんが夕飯を用意する間、ダニエラさんは休憩を取る
助手のシュエブさんが夕飯を用意する間、ダニエラさんは休憩を取る
 学校が終わると、家族の時間が始まる。ダニエラさんは母親業も楽しむ
学校が終わると、家族の時間が始まる。ダニエラさんは母親業も楽しむ
 子どもたちと一緒の時間には、仕事のことは考えない
子どもたちと一緒の時間には、仕事のことは考えない
 毎週月曜日に販売部門のチーム全員でミーティングを行い、1週間の予定を確認する
毎週月曜日に販売部門のチーム全員でミーティングを行い、1週間の予定を確認する
 アンカレッジにリカーショップを3店舗経営する顧客のブライアン・スワンソンさんと
アンカレッジにリカーショップを3店舗経営する顧客のブライアン・スワンソンさんと
 K&Lディストリビューターズ社における2015年のビール販売数は270万ケース
K&Lディストリビューターズ社における2015年のビール販売数は270万ケース
 配達担当ともお互い助け合って働く
配達担当ともお互い助け合って働く
 カリフォルニア州の有名醸造所ラグニタスの営業が訪問
カリフォルニア州の有名醸造所ラグニタスの営業が訪問
 できるだけ自然の中へと出掛けるようにしている
できるだけ自然の中へと出掛けるようにしている
 たとえば「バード・クリーク」へ釣りに出掛ける
たとえば「バード・クリーク」へ釣りに出掛ける
 アンカレッジから20分の場所にある「バード・クリーク」はギンザケ釣りで有名だ
アンカレッジから20分の場所にある「バード・クリーク」はギンザケ釣りで有名だ
 およそ10年前にベルーガで仕留めた熊(左)。3頭のゴールデン・レトリバーは親友(右)
およそ10年前にベルーガで仕留めた熊(左)。3頭のゴールデン・レトリバーは親友(右)
 由緒あるアイディタロットの犬ぞりレースを完走したマッシャー(犬ぞり使い)だけが特別に使用できる自動車ナンバー。数字の22は、2008年に獲った過去最高順位
由緒あるアイディタロットの犬ぞりレースを完走したマッシャー(犬ぞり使い)だけが特別に使用できる自動車ナンバー。数字の22は、2008年に獲った過去最高順位
 犬たちとの散歩はとても楽しい
犬たちとの散歩はとても楽しい
 明るい毛色をした2頭はミラ(16歳)とオスカー(ミラの息子)。もうあまり長く生きられないため、昨年、新しい犬アリーナを家に迎え入れた。アリーナはミラとオスカーから大歓迎された
明るい毛色をした2頭はミラ(16歳)とオスカー(ミラの息子)。もうあまり長く生きられないため、昨年、新しい犬アリーナを家に迎え入れた。アリーナはミラとオスカーから大歓迎された
 人里から離れてはいるが、孤立はしていない。ハンスさんとその友人、そして忠誠心が強いという友人の飼い犬アルビ
人里から離れてはいるが、孤立はしていない。ハンスさんとその友人、そして忠誠心が強いという友人の飼い犬アルビ
 クリスティーンさん、仕事部屋にて
クリスティーンさん、仕事部屋にて
 ホステットラー夫妻は旅行者のために、さまざまな環境保護アクティビティーを提案する
ホステットラー夫妻は旅行者のために、さまざまな環境保護アクティビティーを提案する
 クリスティーンさんはパラグアイでチーズ作りを学んだ
クリスティーンさんはパラグアイでチーズ作りを学んだ
 ハンスさんは35年以上前からグアラニーの森のとりこだ
ハンスさんは35年以上前からグアラニーの森のとりこだ
 鶏の世話も毎日欠かさない
鶏の世話も毎日欠かさない
 ハンスさんは小型飛行機で保護区域一帯を見回り、違法な行為が行われていないか監視している
ハンスさんは小型飛行機で保護区域一帯を見回り、違法な行為が行われていないか監視している
 自宅の畑にて
自宅の畑にて
 手先が器用なハンスさんは、パラグアイの自宅を自ら改築し、水周りや電気設備などを整えた
手先が器用なハンスさんは、パラグアイの自宅を自ら改築し、水周りや電気設備などを整えた
 森を散歩中の夫妻
森を散歩中の夫妻
 休憩にはパラグアイの伝統的なマテ茶を用意
休憩にはパラグアイの伝統的なマテ茶を用意
 有機農場「ニュー・ガームバッハ」とビニールハウス、夫妻の自宅
有機農場「ニュー・ガームバッハ」とビニールハウス、夫妻の自宅
 1984年、マンサー氏は初めてボルネオ島を訪れた
1984年、マンサー氏は初めてボルネオ島を訪れた
 熱帯雨林の中を移動して暮らすプナン族
熱帯雨林の中を移動して暮らすプナン族
 マンサー氏、アルベルト・ヴェンツァーゴ撮影、1986年
マンサー氏、アルベルト・ヴェンツァーゴ撮影、1986年
 雑誌用の写真撮影にて、アルベルト・ヴェンツァーゴ撮影、1986年
雑誌用の写真撮影にて、アルベルト・ヴェンツァーゴ撮影、1986年
 熱帯雨林の乱伐はとどまるところを知らない
熱帯雨林の乱伐はとどまるところを知らない
 当時の連邦閣僚ルート・ドライフース氏と共にセーターを編むマンサー氏、ベルンにて、1993年3月
当時の連邦閣僚ルート・ドライフース氏と共にセーターを編むマンサー氏、ベルンにて、1993年3月
 熱帯木材の輸入中止を訴え、環境保護活動家のマーティン・ヴォッセラー氏と共にハンガー・ストライキを行うマンサー氏、1993年、ベルンにて
熱帯木材の輸入中止を訴え、環境保護活動家のマーティン・ヴォッセラー氏と共にハンガー・ストライキを行うマンサー氏、1993年、ベルンにて
 マンサー氏はたびたびヨーロッパへと戻り、マレーシアの原住民が住む熱帯雨林の保護を訴えた(Keystone)
マンサー氏はたびたびヨーロッパへと戻り、マレーシアの原住民が住む熱帯雨林の保護を訴えた(Keystone)
 プナン族もバリケード封鎖で熱帯雨林伐採に抵抗した
プナン族もバリケード封鎖で熱帯雨林伐採に抵抗した
 マンサー氏はプナン族と同じように狩りをし、魚を獲った
マンサー氏はプナン族と同じように狩りをし、魚を獲った
 サイチョウにエサをやるプナン族の女性
サイチョウにエサをやるプナン族の女性
 亡くなった首長のアラ・ポトン
亡くなった首長のアラ・ポトン
 プナン族の首長(右)とマンサー氏(左)
プナン族の首長(右)とマンサー氏(左)
 現在も移動民族として生活するプナン族の男性
現在も移動民族として生活するプナン族の男性
 行方不明になる直前のマンサー氏、サラワクにて、2000年5月
行方不明になる直前のマンサー氏、サラワクにて、2000年5月
 熱帯雨林の日没
熱帯雨林の日没
 マサイ族の戦士の信頼を得ることは、マサイ族のコミュニティーと関係を築く上で重要だ
マサイ族の戦士の信頼を得ることは、マサイ族のコミュニティーと関係を築く上で重要だ
 ムクルにある革製品のアトリエで新しいバッグのデザインについて話し合う
ムクルにある革製品のアトリエで新しいバッグのデザインについて話し合う
 マサイ族風のビーズアクセサリーの製作には、良い視力と器用な手先が必要だ
マサイ族風のビーズアクセサリーの製作には、良い視力と器用な手先が必要だ
 ガブリエルさんは会社で数少ない男性のエキスパート
ガブリエルさんは会社で数少ない男性のエキスパート
 マリーナさんはマサイ族の集落や小屋を訪れ、部族の人たちと会う
マリーナさんはマサイ族の集落や小屋を訪れ、部族の人たちと会う
 海外からの注文に応えるには継続的な生産計画が必要だ
海外からの注文に応えるには継続的な生産計画が必要だ
 次の世代の子どもたちが、マリーナさんの会社で働きたいと思うか、それとも町や都会に出たいと思うかはまだ分からない
次の世代の子どもたちが、マリーナさんの会社で働きたいと思うか、それとも町や都会に出たいと思うかはまだ分からない
 ムクルにすむマサイ族の女性たちに会いに行くには、でこぼこ道を50キロ走らなければならない
ムクルにすむマサイ族の女性たちに会いに行くには、でこぼこ道を50キロ走らなければならない
 アルーシャの販売店舗で新しいスタッフを指導する
アルーシャの販売店舗で新しいスタッフを指導する
 移動中の不測の事態を防ぐため、タイヤの空気圧を点検することも重要なことの一つ
移動中の不測の事態を防ぐため、タイヤの空気圧を点検することも重要なことの一つ
 農場暮らしでは、門を閉めることを忘れてはならない
農場暮らしでは、門を閉めることを忘れてはならない
 マリーナさんのモンゴル風テントの家を見張る2匹の犬、ピッコラとビュッフォ
マリーナさんのモンゴル風テントの家を見張る2匹の犬、ピッコラとビュッフォ
 早朝でも仕事の電話に出る
早朝でも仕事の電話に出る
 落下式トイレは、ここでは贅沢な設備だ
落下式トイレは、ここでは贅沢な設備だ
 マリーナさんの家では「ベランダ」が一番落ち着ける場所だ
マリーナさんの家では「ベランダ」が一番落ち着ける場所だ
 少ない自由時間を利用して読書をする
少ない自由時間を利用して読書をする
 ビーズアクセサリーのアトリエには、いつも誰かが遊びに来る
ビーズアクセサリーのアトリエには、いつも誰かが遊びに来る
 朝起きて、まず最初に愛馬「ピンクフィズ」の体調をチェック
朝起きて、まず最初に愛馬「ピンクフィズ」の体調をチェック
 夕方2匹の愛犬を連れて長い散歩に出ることが、マリーナさんとっては良い気晴らしだ
夕方2匹の愛犬を連れて長い散歩に出ることが、マリーナさんとっては良い気晴らしだ